ラジオホームドクター
岐阜県における小児救急医療(12月4日木曜日)小児救急医療の問題点・改善の為の啓発・発達障害の早期療育の必要性と地域の協力(12月5日金曜日)
昨日に続きましてまず小児救急医療の問題点の背景を考えたいと思います。
1)近年の出生率1.3と危機的な減少と晩婚化があり 2)新米の両親に育児経験・育て方の習得機会のないこと 3)共働きのため子供との接触機会が十分でないこと 等個々の状況は異なりますが、親(保育者)にとって昼間・ 夜間・日祭日を問わず乳幼児の急変・急病・高熱等は、不安心配で些細なことでも専門の小児科医等にすぐに適切な処置を受けなければと思う気持ちは判らないではありません。 昨日もお話しましたが、全国の急患センターにおける15歳以下の小児救急患者は人口が15%以下なのに50.4%と半数を超えています(其の内5歳以下が75%).病院においては日中の小児患者は8.1%程度ですが救急患者は25.4%と高く小児時間外救急診療の集中化が小児科医の過労働や疲弊化となり32時間連続勤務や月8回当直など過労死や自殺などの原因として問題視されています。また小児救急のうち79%が1次・16%が2次・5%が3次対応であること・1歳未満の重症度が高いこと(0.3%は集中治療の提供が必要)などの報告もあります。 さてここで出産育児など小児を取り巻く岐阜県の実態はと申しますと 1)母子手帳に始まる妊婦健診、出産時の補助、乳児健診、乳児医療費助成制度等にあまりにも地域格差目立ちます。 2)医療機関の対応力向上・医療資源の集約化・拠点病院の整備等が図られ 3)小児救急電話相談事業#8000は年々利用され1.5倍に増加 4)母と子の健康サポート事業も実施されています これらは都市部・准都市部・過疎部・地区のスタッフ人数等で対応が大きく異なります。 岐阜県小児救急協議会は回を重ね、休日診療所・#8000の利用・岐阜市民病院を使った夜間診療・西濃地区でも大垣市民病院でも皆様のご協力にて開始されできる限りの対策を講じています。全県下小児科標榜の病院・診療所の詳細なアンケートがなされ小児科マップも準備されています。医療資源の集約化の検討・小児科医師の育成、小児救急疾患講習会、など過疎対策も講じられています。 しかしながら問題は需要の多さにあります。「小児医療のコンビニ化」と反面超一流の小児科医の診察を当然として「いつでもどこでも安心できる質の高い完結的救急医療」をもとめています。 それを踏まえてもそのようななか、まさに緊急性のない夜間受診の減少をどう図るかです。これまでに行政もいろいろ対策を講じてきましたが地域差も大きく認められました。そこで今述べました約8割の診療所で1次対応できる、発熱している子供さんを翌朝まで両親に看てもらうためにはどのような取り組みが必要なのか。昨日も申し述べましたが夜間でも診ていただけるかかりつけの主治医を持つことが第一です。 その他の解決策として一部ですが4点を考えてみました。 1)地域の支えあい・コミュニティー作り 2)親作り(父親の育児参加の奨励) 3)妊婦健診から10ヶ月児検診までの充実(10ヶ月検診のない地区もあります) 4)育児者に誕生から1歳児までの成長・疾病教育などの充実です。 さてこの担い手は保健師(地区行政の看護師)さんにお願いしたいと思っています(県医師会は県委託事業として各地域の保健師を対象にして講習会を予定しています)。 すでに地域をつぶさによく理解されている皆さんですし、1〜4)を十分実践されていますが、更に産科医・小児科医の協力を得て子供の発達・疾病・事故などを一緒に勉強していただきます。その上で母子手帳を渡す時点から訪問を繰り返し、家庭環境の確認・夫婦二人の考え方・出産準備・心構えなどの構築を始めます(新米ママのコーチになります)。出生から3歳程度までは信頼して気軽に相談出来る子育てチームの核になってもらいます。 期待できる補助効果として 両親の楽しい子育ての実感と保育園・幼稚園・学校での事業参加 家庭力の確立といじめ・不登校など予防 6%の発生とも言われている発達障害児の早期発見と早期療育さらに地域での子育てと、ノーマライゼーションの定着 親として安心・安全・成長が図られ、出生率の向上にも結びつくものと考えます。 最後に地域でしっかりと対応していかなければならない、発達障害児についてお話させていただきますと、自閉症とか広範性発達障害児は社会性やコミュニケーションが苦手でまた音感・感覚が鋭く抱っこされたりすることが強烈に痛かったりで、様々な個人差を持っていますが、たとえ目が合わなくても、またそこにじっとして居れなくても感情や心はなんら変わりなく傷つきやすいのです。しかしその特性を知らずにいますと、発達にとっての大切な時期に、しかったりテレビに任せたりで知的にも動作にも遅れてしまい就学時にとても問題にされます。ここに知識を持った保健師さんが早い時期に発見し受診を促しそして地域ご近所さんのサポートを促すことが若い両親にとってとても大切だと考えます。 |
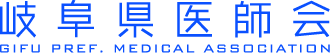
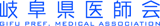
全国各地にて医師不足による病院閉鎖あるいは小児科・外科など診療科の閉鎖が行われていることは周知のとおりですが、岐阜県においても同様に起きておりあるいは悪化に向かっている現状を理解していただきたいと思います。岐阜県は人口比面積比の両面から見ましても全国的に有数の医療過疎地となっています。そんな中でひとつの解決策としましてドクターヘリが導入されようとしております。夜間運行、維持経費など問題も多く、あるいは利用した際の費用など検討されなければなりません。
さて先ほどの問題の中には産科急病人の受け入れ問題、あるいは安易なタクシー代わりの利用などの問題もございますが、今日は小児救急の問題を話したいと思います。夜間・日祭日を問わず乳幼児の救急・急病は保育するものにとって、不安心配で些細なことでも専門の小児科医等にすぐに適切な処置を受けなければと思う気持ちは判らないではありません。
やけど・外科的な処置・脳神経疾患・クループ・脱水症など年齢等を考え緊急性の高いものもけして少なくはありませんが、発熱・腹痛・咳・泣き止まない・鼻水など多くの場合は電話対応で翌日に受診していただくことが可能であることが多いようです。私もよく夜間も受けますが(小児外科に携わっていました)診た時点で処置をして投薬して、初めて安心してご家族に説明しています。
ある報告ですが、全国の急患センターにおける15歳以下の小児救急患者は人口が15%以下なのに50.4%と半数を超えています(其の内5歳以下が75%).病院においては日中の小児患者は8.1%程度です、が救急患者は25.4%と高く小児時間外救急診療の集中化が小児科医の過労働や疲弊化となり、32時間連続勤務や月8回当直など過労死や自殺などの原因として問題視されています。女性医師の増加も負担の軽減に結びつくとは限りません。小児救急のうち79%が1次・16%が2次・5%が3次対応であること・1歳未満の重症度が高いこと(0.3%は集中治療の提供が必要)が報告されています。
岐阜県小児救急協議会は回を重ね様々な検討をしておりますが、各医療圏(岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨〈高山・飛騨・白川部会、下呂部会〉)においてもそれぞれの提案検討がなされました。休日診療所・#8000の利用・岐阜市民病院を使った夜間診療・西濃地区でも大垣市民病院でも皆様のご協力にて開始され充実してきました。全県下小児科標榜の病院・診療所の詳細なアンケートがなされ小児科マップも準備されています。医療資源の集約化の検討に対して小児科医師の育成、小児救急疾患講習会、など過疎対策も講じられています。
さて問題は全国同一であり産科・麻酔科・救急医と同様緊急性が高いことは異論のないところですが、それにも増して需要の多さにあります。「小児医療のコンビニ化」をしている反面、超一流の小児科医の診察を当然として「いつでもどこでも安心できる質の高い完結的救急医療」をもとめています。それを踏まえてもそのようななか、まさに緊急性のない夜間受診の減少をどう図るかです。その状況を敢えて分析してみますと、先ず社会情勢の不安定化・初産の高齢化・出生数の減少があり、育児経験不足・家族本人の仕事の多様性・地区での疎外性・価値観の変化等々があります。一次病院・診療所を受診された際患者さんとして診療時間帯に来ていただける場合と、夜間・休日などでは態度・対応があまりにも違う場合が多いことを感じられていらっしゃることと思います。他の仕事の最中であったり医療スタッフも不十分なことがおおいからです。初診で診た患者さんは病態の変化の対応策も含めて一貫して治療し治癒までは主治医・かかりつけ医に責任があります(診療契約)。主治医であれば急変することが当たり前の小児医療はそれが時間外であっても、ますます疲弊することになりますが、それは誰もが容認できるものではないでしょうか。辛いのは他院からの無責任な見放しです。(たしかにフリーアクセスですし専門外の場合もあります。精一杯の治療や充分な説明にもかかわらずの訴訟の多さも萎縮診療に結びつき見放しにつながることも理解できます。)
現実として病院で少ない小児科医として働くことはあまりにも過酷で、体力的にも精神的にも燃え尽きて、開業の道を選びます。免疫機能が未熟な乳児幼児は軽症のことが多く時に重症化しますが、主治医としとてその子をいつも診ており理解している場合は問題ありません。インフォームドコンセントでその小児の特性をよく理解していただき、発熱・痙攣・嘔吐下痢などにも余裕を持ってお家で看ていただいて翌日の外来受診でも大丈夫です。
若い医学生が『進んでこぞって小児科医になりたく思う社会環境』を皆さんで作っていただきたいものです。
明日は地域で子供たちを育てることを考えてみたいと思います。