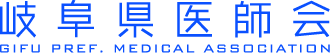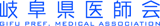ラジオホームドクター
ノロウイルス感染症について(1)
最近、冬季を中心にノロウィルス感染症が報告されています。これからノロウィルス感染症は急増するシーズンに入ります。
県内でも例年、学校や老人施設・職場などでの集団発生例が報道されています。今回は、ノロウィルス感染症とは何か?この感染症の原因・対応・予防などを中心に考えていきたいと思います。
Q:最近、集団感染が報告されているノロウィルス感染症ですが、そもそもノロウィルスとはどのようなものでしょうか
ノロウィルスは食中毒および感染性胃腸炎の代表的な原因の一つです。例年、10月から11月にかけて流行が始まり、その後、急速に増加して12月から1月に流行のピークをむかえます。
このウィルスは冬季を中心に流行し、形態学的分類では小型球形ウィルスと分類されています。かってはノーウオークウィルス(Norwalk-like viruses)と呼ばれていました。 しかし、2002年に国際ウィルス命名委員会によりノロウィルスと命名され、世界でこの名称が統一され用いられるようになりました。 このウィルスは著しい下痢や嘔吐を引き起こすことも多く、医療整備が遅れている国々では、このウィルスの感染により毎年20万人以上が死亡しているとも言われます。また最近は米国や日本などの高齢者施設でも、入居者の日常的な流行感染症となり、予防学的にも重要な感染症と言えると思います。
Q:ノロウィルスの症状について教えてください
症状は嘔吐・下痢・腹痛などの消化器症状です。感染から発症までの潜伏期間は24時間から48時間です。
ノロウィルスがヒトに侵入すると、ウィルスは小腸の上皮細胞に感染して、上皮細胞を委縮・脱落をさせ、これにより下痢を引き起こします。 下痢・嘔吐による重症の脱水や誤嚥などの合併症が無ければ、通常の経過としては消化器症状が1〜2日間続いた後、治癒することが一般的です。 ただし、症状が消失しても、数日間はウィルスが糞便中に排出されます。 ノロウィルスは100個程度のウィルスが体内に入っただけでも感染を引き起こします。 このような少量のウィルスが体内に侵入しただけで感染を引き起こしてしまう事が、短期間で集団感染を引き起こし、予防を難しくしている要因となっていると思われます。
Q:このウィルスの感染経路ついて教えてください
ノロウィルスの感染経路は口からウィルスが入る経口感染です。
1.食べ物からヒトに感染する食中毒としての感染経路、2.感染者の排泄物中のウィルスとの接触のため、ヒトからヒトに感染を引き起こす感染性胃腸炎としての2つの感染経路があります。 法規上は前者は食中毒としても扱われ、後者は感染症として扱われます。 ただし集団感染では両者が混在する事もあり、対応に混乱が生じる事もあります。
ノロウィルスによる感染が起こったら、届け出義務があるのでしょうか
1.ノロウィルスによる食中毒が発生した場合は、食品衛生法上、保健所に届けなくてはなりません。
2.感染性胃腸炎の場合は、感染症法5類感染症と分類され、定められた小児科医療機関のみでの報告数を集計しています。 ノロウイルス感染症について(2)
Q:まず、食中毒としてのノロウィルスの感染経路について教えてください
ノロウィルスの食中毒の原因食品としては、生かきなどの二枚貝、またはこれらを含む食品や献立が大半を占めています。ノロウィルスは自然界では、感染者の排泄物から汚水中に移行し、これが浄化処理をかいくぐり、河川から海へと排出され、海水中に拡散されます。海水中のウィルスは、二枚貝により大量の海水とともにを取り込まれ、濃縮されます。この二枚貝をヒトが生で食べることによりウィルスに感染します。
そして感染者から排泄されたウィルスは再び汚水中に入り循環を繰り返します。 毎年、日本では冬場に生カキなどの二枚貝を生で食べる習慣があり、これが冬季にノロウィルスの食中毒が多くなる要因の一つとなっています。 また二枚貝の調理の際に、ウィルスにより、調理器具が汚染される事があります。 このウィルスに汚染された調理器具を介して、他の食品へと二次汚染が拡がり、二次感染を引き起こします。 通常、二次汚染された食品中ではノロウィルスは増殖しません。食品はウィルスの運び屋となり、その汚染された食品を食べる事により感染が引き起こされます。 このため二枚貝などを調理には、出来るだけ専用の調理器具を用意する事が大切です。 使用後はよく洗浄・熱湯消毒を行いウィルスを除去することが大切です。 もちろん調理前後の手洗いは食中毒予防において最も重要です。
Q:感染性胃腸炎としてのノロウィルスの感染経路について教えて下さい
ノロウィルスは感染者の吐物や糞便といった排泄物中に大量に存在します。この排泄物中のウィルスが経口的に人体に侵入し、ヒトからヒトへの感染を引き起こします。
Q:ノロウィルスの食中毒の予防・対応について教えてください。
石鹸による手洗いは食中毒の予防上重要です。ただし、ノロウィルスを失活化するには、エタノールや逆性石鹸はあまり効果がありません。
ウィルスの失活化には加熱と次亜塩素酸の消毒が有効です。 食品中のウィルスは加熱により容易に失活化する事ができます。 食品の中心温度が85℃で1分以上、煮沸なら1分での加熱処理で充分に失活化されます。 調理器具も、85℃で1分以上の加熱が有効でしょう。 また調理器具を塩素濃度200ppmの次亜塩素酸に浸し、消毒することでもウィルスを失活化させる事ができます。この次亜塩素酸による消毒は、塩素系の漂白剤でも代用できます。 調理者の白衣もウィルスが付着し二次汚染源になった例もあり、白衣をこまめに交換する事も大切です。ただし手指の消毒には次亜塩素酸は皮膚炎を起こすため使用できません。手洗いは石鹸でこまめに行ってください。
Q:感染性胃腸炎に対する感染拡大予防について教えてください
最近では、流行はリアルタイムにインターネットを通じて、サーベイランスとして公開されています。
これで流行の把握ができるようになりました。地域で流行が認められる時、突然の下痢や嘔吐を発症した場合には、感染性胃腸炎と考え対応したほうが良いでしょう。 ウィルスは発症者の排泄物に存在しています。このため排泄物の処理が感染拡大防止において重要となります。 患者の排泄物・汚染されたおむつを処理する場合には使い捨ての手袋・マスクを着用し、汚染物が周囲に飛び散らないよう、ペーパタオルで拭き取った後、密閉処理する事が大切です。 排泄物が付着した床やシーツは、マスク・使い捨て手袋を着用し次亜塩素酸でふき取りまたは浸し消毒します。 この時、吐物や糞便が乾燥する前に処理する事が非常に重要です。 特に狭い空間では、ウィルスは乾燥した排泄物から塵のように空中に漂い、これを吸い込むことにより感染をひき起こします。 このため汚染物の処理は乾燥する前に行い、使用したペーパータオルなどは次亜塩素酸につけた後、密閉処理する事が大切です。 感染性胃腸炎の場合には、この汚染物の取り扱いが、感染の拡大防止に最も重要です。 また、頻回にヒトが接触するドアノブなどは、ウィルスに汚染されやすく、次亜塩素酸で頻回にふき取り・消毒する事が大切です。 流行時には、施設内に出入りするヒトには、入り口での手洗いや消毒・マスクの着用によりウィルスが持ち込まれないようにする事も大切です。 学校や老人施設などで患者が一度に多く発生する原因としては、食中毒の場合を除き、感染者により施設内にウィルスが持ち込まれることにより起こります。 時には外部からの人の出入りやサービスの制限も必要となることもあるでしょう。 冬季はインフルエンザウィルスなどの感染も同時に流行することも多く、マスクや手洗い・環境衛生の整備は同時に流行する感染症の予防においても非常に重要です。 特に高齢者や幼児などでは、下痢症状のため、おむつの交換回数が増加します。このため交換作業に手間を取られ、汚染されたおむつの処理や消毒作業が充分にできずに、感染が拡大してしまう事があるので注意が必要です。
Q:ノロウィルスに対するワクチンや薬剤はありますか
現在のところ、ノロウィルスに対するワクチンは未開発で、ありません。また増殖を抑える抗ウィルス剤も開発されておりません。
Q:ノロウィルスに感染してしまったら、検査・治療はどうするのでしょうか
ノロウィルスは多数の遺伝子型が存在するため、ヒトは何回でも感染します。診断は便中のノロウィルスの抗原や遺伝子をしらべる検査がありますが、一定の時間もかかり、インフルエンザウィルス検査のように簡便には行われてはおりません。
通常は脱水症状に対して輸液などを行い、整腸剤などを内服する対処療法が行われます。
Q:最後に感染症の流行時には、まず何に注意すればよいのでしょうか
あらゆる感染症の流行時について大切な事は、その感染症について正しく理解し、予防対策をとる事が重要です。
あまり情報が混乱してしまうと、過剰に反応したり、時には間違った情報に惑わされてパニックになる場合があります。まずは流行している感染症を正しく理解し、冷静に対応することが最も大切だと思います。 最近ではインターネットを通じて、自分が住んでいる地域で、どのような感染症が流行しているのか把握し監視していく、感染症サーベイランスが行われ、公開されています。 このような情報も上手く利用しながら、流行している感染症を把握し、適切な時期に適切な方法で冷静に対応していくことが最も大切だと思います。 |